本書は、グラハム・マーシュ、ジューン・マーシュ、ポール・トリンカの編著した『デニム・バイブル』 という本です。
リヴェットなどデニムのディテールにこだわった記事から掘り起こし、デニムの歴史を現代にまで展開した精力的な本です。
時代ごとに章立てされ、ほとんどデニムの写真や着用者の写真で埋めています。章冒頭の時代背景と無数の写真には簡潔な説明があります。
デニム好きが持っておきたい本です。
デニム・バイブル:カウボーイからキャットウォークまで
リーバイ社に注目
アメリカのデニムというとリーバイ社のリーバイス・ジーンズを思いがち。
もちろん、同社のデニムも多くとりあげリーバイスの歴史をフォロー。
次の写真はリーバイ・ストラウス社が1915年にパナマ太平洋国際博覧会の製造実演会場で行なったデニムの製造風景です。

リーバイ・ストラウス社が1915年にパナマ太平洋国際博覧会の製造実演会場で行なったデニムの製造風景(グラハム・マーシュ、ジューン・マーシュ、ポール・トリンカ『デニム・バイブル』 田中敦子訳、 スペースシャワーネットワーク、2006年、43頁)
右側にはきっちり裁断されたデニム地がミシン縫製を待っています。
リーバイ社以外に注目
でも本書はリーバイ社に振り回されるわけではありません。
リーやエロッサーハイネマンなど他のデニム・メーカーも忘れていません。他社の記事も意外に多くて楽しめます。
次の写真はエロッサー・ハイネマン社の「キャント・バステム」(CAN’T BUST’EM)商標の詳細です。銅製リベットではなくバータックでポケットを補強しているのを強調しています。

エロッサー・ハイネマン社の商標「キャント・バステム」パンフレット/1919年(グラハム・マーシュ、ジューン・マーシュ、ポール・トリンカ『デニム・バイブル』 田中敦子訳、 スペースシャワーネットワーク、2006年、43頁)
次の写真はエロッサー・ハイネマン社のキャントバステム製造工場の様子です。
ミシンと縫製工と縫糸がずらりと並んでいます。
足踏式ミシンか、それに電動モーターを付けたミシンかが写真では分かりません。
左奥のデニムの山は、ミシンのキャントバステム加工を待つ半製品でしょう。

エロッサー・ハイネマン社キャントバステム製造工場(グラハム・マーシュ、ジューン・マーシュ、ポール・トリンカ『デニム・バイブル』 田中敦子訳、 スペースシャワーネットワーク、2006年、42頁)
生地デニムに注目
当然、デニムまたはジーンズは衣料品となる前に生地の段階がある訳ですが、これを次のように述べています。
デニムの世界が広がりそうでワクワクします。
デニムという言葉は、今日では広く知られているが、かつてはもっぱらアメリカの工場内で使われるだけだった。リーヴァイスが使ったデニム生地は、当初はニューハンプシャー州にあるアモスケイグの巨大工場で製造されていた。だが、1915年以降、リーヴァイ・ストラウス社はノースキャロライナ州のコーンミルズ社からデニムを仕入れるようになる。現在でもコーンミルズ社は世界有数のデニムメーカーである。ラハム・マーシュ、ジューン・マーシュ、ポール・トリンカ編『デニム・バイブル』 田中敦子訳、 スペースシャワーネットワーク、2006年、22頁

グラハム・マーシュ、ジューン・マーシュ、ポール・トリンカ編『デニム・バイブル』 田中敦子訳、 スペースシャワーネットワーク、2006年、22頁。
まとめ
この手の本は《文化史》で終わりがちですが、本書はそれで終わっていません。
デニム生地の製造工場とデニム・パンツの製造工場の写真と説明があって(23頁、27頁・42頁)、アメリカの大量消費社会を支えた大量生産工場の具体的なイメージを経済史からもわかります。


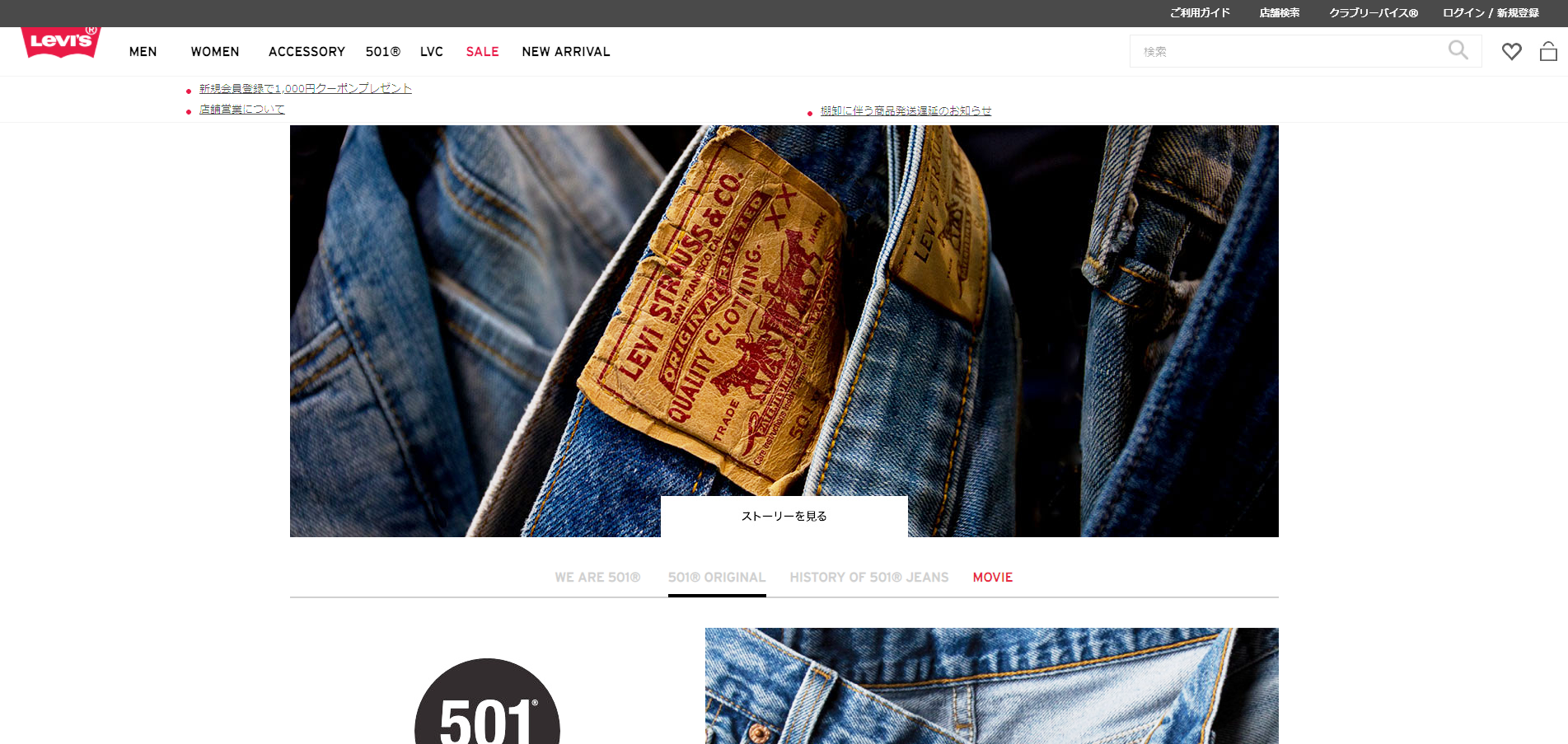


コメント